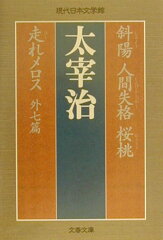「斜陽」は、敗戦により没落して行く貴族の姿を描いた作品です。
走れメロスや人間失格と並んで太宰治の代表作といわれている作品ですから、興味のある方も多いのではないでしょうか。
この記事では「斜陽」のあらすじを、簡単・簡潔に説明します。
読書感想文を書く時にも役に立つと思いますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。
[ad#co-1]
「斜陽」のあらすじを簡単・簡潔に短く紹介!
「斜陽」あらすじ
戦後、裕福な暮らしから一転して、ほとんどの財産を失った華族の娘かず子。
最愛の母は病気で床に伏し、戦争から帰還した弟は、残り少ない財産を食いつぶす毎日。
そんな中、ある男に思いを募らせるかず子。
ゆるやかに破滅に向かう生活の中で、かず子の意識革命が始まります。
[ad#co-1]
「斜陽」の登場人物を1行で紹介!
「斜陽」の主な登場人物は次に4人です。
この4人それぞれに、太宰自身の姿が投影されていると言われています。
「斜陽」の登場人物
- かず子:華族の長女で29才。離婚歴があり流産も経験
- 母 :かず子の母。産まれながらの貴婦人で病弱
- 直治 :かず子の弟。麻薬中毒の不良息子で出征後行方不明
- 上原 :直治が慕う小説家。上流階級を嫌い酒びたりの生活
[ad#co-1]
「斜陽」の見どころ
太宰治は、かず子を通して「革命」を描こうとしました。
それは、政治の世界の社会主義革命ではなく、かず子の人間としての革命です。
そのため、この作品の最大の見どころは、かず子の意識の変化にあると言えます。
あらすじとともに、その変化を見て行きましょう。
没落しているとはいえ、浮世離れした生活に慣れているかず子
物語は、かず子の母が朝の食卓でスープを飲むシーンから始まります。
その仕草が「ひらり」と表現されているところに、没落したと言えども、華族の生活がいかに浮世離れしていたかが象徴されていますね。
[ad#co-1]
東京から伊豆へ…体調を崩していく母
もともと東京のお屋敷で暮らしていたかず子たち。
しかし、経済状態の悪化により、伊豆の別荘へと引っ越さざるを得なくなります。
かず子はそこで母と二人、つましいながらも平和な生活を送りますが、次第に母は体調を崩して行きます。
また、自分たちに生活力のない事を自覚しているかず子の心に、不安が忍び寄ります。
[ad#co-1]
直治の帰還と平和な生活の終わり
かず子の弟、直治は、学生時代から麻薬に手を出し多額の借金を作る不良息子。
徴兵された後、南方で行方不明になっていました。
ところがある日、その直治が実は生きているという事を、叔父から知らされます。
ひょっこりと伊豆の別荘に姿を現した直治。
その時、かず子は平和な生活の終わりを確信するのでした。
[ad#co-1]
直治の荒れた生活と「ひめごと」
帰還してからの直治は、以前から慕っていた小説家の上原と、遊び呆ける生活を繰り返します。
かず子は6年前、直治にお金を届けるため、一度だけ上原に会いに行きました。
そしてその時、上原とある「ひめごと」を持つことになったのです。
母の死とかず子の恋
母の容体が悪化するに連れ、6年前の「ひめごと」が鮮烈になるかず子。
かず子の上原への想いが日に日に高まって行きます。
かず子はたまらず上原に3通の恋文を書きますが、返事は来ませんでした。
[ad#co-1]
華族の滅亡
そしてとうとう、母が亡くなります。
秋の黄昏時に死んだ日本最後の貴婦人。
このシーンがまさに「斜陽」と言えるでしょう。
かず子の自立と直治の死
母の死後、かず子は自分の願望を実行に移す決意をします。
上原に会うため東京に出たかず子は、ついにその目的を果たします。
しかし、かず子が幸福の中目覚めた朝、伊豆の別荘では直治が自殺を遂げていました。
かず子の意識革命
その後、かず子は上原の子を身ごもります。
そして、世間から何と言われようと、その子を一人で育てて行く決意をします。
母は貴族のまま、弟は民衆になり切れず、旧世界に消えて行きました。
しかし、かず子は民衆の子を産む事で民衆となり、新しい世界で生きる事を選びました。
これがかず子の「革命」だったのです。
[ad#co-1]
「斜陽」の読書感想文で書くべき3つのポイント!
「斜陽」を読むときには、次の3つのことに注目してみてください。
「斜陽」の理解を深める3つのポイント
- ①作品が書かれた背景
- ②作品のテーマ
- ③作品が社会に与えた影響
より良い感想文を書くためには、作品への深い理解が必須です。
この3点をぜひおさえておきましょう。
[ad#co-1]
ポイント①「斜陽」という作品の背景:アントンチェーホフの「桜の園」との関係
「桜の園」は、ロシアの作家アントン・チェーホフ作の戯曲で、帝政ロシアの没落貴族を描いています。
津軽の名家出身だった太宰は、戦後の変わり果てた生家の姿を見て「桜の園」そのままだと感じ、それが「斜陽」の着想へとつながったといわれています。
ポイント②「斜陽」のテーマとなっているものは「逃亡と再生」
「斜陽」の根底に流れるテーマは「滅亡と再生」です。
それは、華族から民衆へ、というかず子個人の生まれ変わりのみならず、日本が新しい時代へと突入した事も意味しています。
そして、母と直治の死(古い日本の終わり)と、かず子の出産(新しい日本の始まり)が、それを表現していると言えるでしょう。
「斜陽」が描かれた1947年は、敗戦から復興へと向かう、日本の過渡期と言える時代でした。
だから多くの人々の共感を呼び、ベストセラーになったんですね。
[ad#co-1]
ポイント③「斜陽」という作品の影響力:「斜陽族」という言葉を生み出した
「斜陽」が発表されて以降、第二次大戦後に没落した上流階級の人々を「斜陽族」と呼ぶようになりました。
それは1948年の流行語となり、これをきっかけに「◯◯族」という呼び方が定着しました。
「斜陽」の社会的影響力の大きさがうかがわれるエピソードですね!
斜陽あらすじまとめ
今回は、太宰治の「斜陽」について解説しました。
いかがでしょう、「斜陽」に描かれた世界は、確かに現代の生活とはかけ離れています。
しかし、その根底に流れる「滅亡と再生」のテーマ、そして「愛する人の子供を産みたい」というかず子の気持ちは、いつの時代にも通じる普遍的なものだと言えます。
そう考えれば、この作品が、もっと身近に感じられるのではないでしょうか。
本文で紹介しましたが、チェーホフの「桜の園」は「斜陽」の世界を理解するためにはとても重要です。
興味のある方は、ぜひ「桜の園」も読んで見てくださいね!
[ad#co-1]